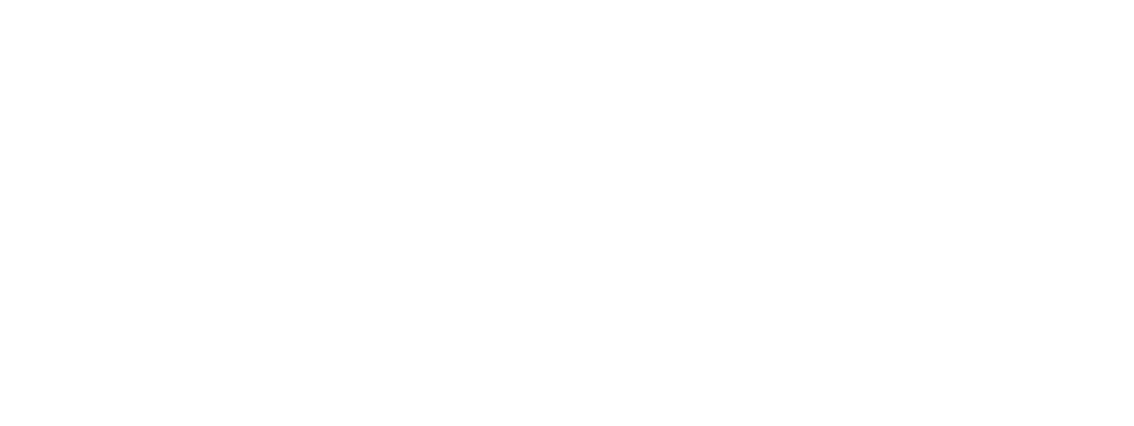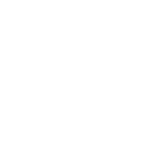会期: 2022年5月21日(土)〜6月5日(日)
会場: es quart (エス クォート)
住所: 東京都台東区千束3-4-3 千束河合荘3F
開館時間: 12:00〜19:00
休館日: 月曜日・木曜日
観覧料: 無料
_____
写真家・長田果純の個展「平凡な夢」を、5月21日(土)より、es quart にて開催いたします。会場では初の写真集『平凡な夢』を販売。展示では写真集未掲載のアザーカットやインスタレーションなどを用いて、平凡な夢の渦中にいた長田の深層心理を再現し、写真集とは異なる「体験」を鑑賞者に伝えようと試みる。
長田は1991年生まれ、静岡県出身。東京都在住。14歳から独学で写真を撮り始める。現在はファッション、アーティスト写真、ポートレイト、雑誌への寄稿など、活動は多岐にわたる。
感染症のパンデミックによる長期の自粛生活は、14歳の頃から長田が抱いている「写真に救われる経験」と改めて向き合う機会となった。本個展は2019年の「平凡な夢」の延長線上にあるものだが、もちろん同じものではない。新作「平凡な夢」では、写真を撮ることで自分だけが救われるのではなく、当時の長田のように、つらい経験をしている見知らぬ誰かに届くようにという、祈りが込められている。
作品には「人物」が登場することはほとんどなく、霧、湿度、光の粒、深く沈んだ湖などで構成されている。自身の声に耳を澄ますように、繊細な感情の機微や温もりを写すことは「自らが存在しないセルフ・ポートレート」とも言い換えられるかもしれない。
黄昏の水面に広がる波紋のような静けさを宿す写真は、ときに混沌や艱難辛苦に突き当たりながらも、淡く美しい光を放つ灯台のように、ひときわ目立つ輝きで私たちに「小さな希望が確かにある」ことを示してくれるだろう。長田の作品の集大成とも言える本展示を見て、あなたは何を感じるだろうか。
_____
「平凡な夢 ステートメント」
中学のとき、ある出来事がきっかけで、私は学校に行かなくなった。数カ月はまったく外に出ず、家の中だけで過ごしていた。毎日空が明るくなる頃に眠りにつき、日が沈むと目を覚ましていた。私の心は間違いなく壊れてしまっていたが、その一方で、凪のように穏やかだった。
ある日、たまたま観ていた映画の主人公がフィルムカメラを使っていた。その姿に憧れ、実家の物置小屋に眠っていたフィルムカメラを見つけ、初めて写真を撮った。埃をかぶった年代物のカメラのレンズを通して見た景色はぼんやりとしていたが、いつも繰り返し思い出す夢の中の景色に似ていた。今まで感じたことのない高揚感だった。
庭の花、脱ぎ捨てた靴、古い電球、陽のあたった階段。私の写真に人物が登場することは一度もなかったが、現像した写真を見たとき、あの瞬間何を思っていたか、何を考えていたか、手に取るように分かった。それ以降も、私の写真に人物が写ることはなく、現像した写真には日常の風景が写り続けていた。社会とのつながりを失いたくなかった。
私には、ほとんどと言っていいほど「感情の記憶」がない。誰といて何をしたか、どんなことがあったか──端的に覚えていることや幸福な瞬間は確かにあっても、過ぎてしまえば記憶から消えてしまう。ときどきの感情を思い出せない私にとって驚きだったのは、写真を撮ることを通じて、自分の感情に触れられることだった。そこには確かに感情の軌跡が残されていた。誰のことも信用できず、嘘で埋め尽くされていると思っていた世界で、唯一自分のことだけは信じられるかもしれない。そう思わせてくれたのが写真だった。
今振り返れば、“何かに救われる”という体験をしたのは、このときが初めてだったように思う。それは日記を書くよりも鮮明で、ときに残酷だったが、景色ばかりを写した「私のセルフポートレート」は感情の記憶や心を知る手段となり、日々、私に寄り添い続けた。
*
東京に出てきた頃の日記を見返すと、こんなことが記されていた。
[普通でいること、平凡という難しさ。それはとても壊れやすい。奇跡よりも遠く、手に入らないもの。私はそれを大切にしていくべきだと思う]
私は今でも“平凡”を望んでいて、そんな日々が続くことこそが尊いと信じている。しかし私が体験した“平凡”な夢。それは決して覚めることなく続く、悲劇の始まりだった。
*
あれからずっと愛猫に水と餌を与えるだけで、ほとんどベッドから起き上がらずにいた。夜になると眠れなくなり、近所のコンビニに行く道すがら風を浴びた。身体が何かの膜に包まれているようで、音も、景色も遠い。心と身体が分離していく。街と身体の境目が、自分がどこにいるのかが、今が夢か現実なのかが分からなくなった。
息はしている、けれど生きているのだろうか。現実を生きているよりも、ベッドの上で夢を見続けているほうが、何故だか生きている実感があった。
決して覚めることのない、出口の見えない平凡な夢が、これほど恐ろしいものだとは思わなかった。これが本当に夢だったならどれほど良かっただろう。そう願うことすらできず、屍のように毎日を過ごしていたが、ある日、見兼ねた友人が私を外へ連れ出した。
体を覆っていた薄い膜に穴が空き、目の前の景色たちが私の中に流れ込んできた。太陽は当たり前のように眩しく、湿度が頬の産毛にじっとりとまとわりつくのが分かる。風が柔らかくて温かい。その瞬間、私は無心でシャッターを切っていた。このときのすべてを憶えていたかった。フィルムが光を焼き付けるように、すべてのものを体内に取り込みたかった。気付くと涙が溢れていた。
それからは家の中にいても、それがベッドの上でも、何かに取り憑かれたように写真を撮るようになった。たとえ何も写っていなかったとしても、そこに小さな感情さえ残っていればいい。
日が沈んだ頃にハッと夢から覚めて、今どんな夢を見ていたのか一瞬にして忘れてしまう──ということはなく、少しずつ、本当に少しずつ “平凡な日常”は戻ってきた。
*
美しく見えるものこそ遠く、現実のものとは思えない。私と世界の間にあった薄い膜のようなヴェールがそうさせていたのは間違いないが、今ではもう経験できないあの日々の中で、心の奥底に確かにあった小さな希望のような光を、こぼれ落とすことなく、大切に抱きしめていきたい。
あのときどうやって息をしていたか、どんなふうに世界が見えていたか、一体どんなことを考えていたのか。それが分かるのは、紛れもなく写真を撮っていたからだ。そんなことを思いながらも、私はまだ私のことを理解できていないけれど、窓ガラスに反射する自分と窓の外の世界を重ねるように、偶然でも良いから、どこかの誰かにこの写真が重なることができたなら、あのときの私はちゃんと生きていたのだと証明することができるはずだ。
悲劇ではあるけれど、これは決してつらい物語ではない。ただ、あのときの私のような思いをしている誰かに、届くことを願っている。私が写真によって救われていたように、もしかしたらどこかの誰かに、そっと手を差し伸べることができるかもしれない。
夢から目覚めてしまった私は、もうひとりぼっちじゃない。